10月の五泉。
空はどこまでも青く、風は少し冷たくて心地いい。
そんな中、今年も「えごまの収穫」の季節がやってきました。
…と、ここまでは毎年の恒例行事。
ところが、今年はちょっと違いました。
5月にまいたえごまの種、
残念ながら、ほとんど発芽せず全滅です。😅
原因は“異常気象”——春先の寒暖差と、雨不足と、
そのあと一気に来た猛暑のトリプルパンチ。
自然相手の仕事って、本当に予想がつかない。
「え、まさかここまでか!?」って、何度も空を見上げました。
でもね。
自然はときどき、そんな僕らに“優しいいたずら”もしてくれるんです。
ふと畑の端を歩いていたら、
見覚えのあるギザギザの葉っぱが風に揺れてる。
「おおっ、これはもしや……!」
なんと、去年の落ちこぼれの種たちが、
自力で発芽して勝手に成長していたんです。
これぞ“野生のえごま”。
なんともたくましい。
そんな姿を見たら、「今年はこれで十分」と思えてきました。

🌾 一本一本、丁寧に手刈り
自然に生えたえごまは、列もそろっていなければ高さもまちまち。
でもそれがまた可愛いんです。
一本ずつしゃがみながら電動ハサミで切っていく。
しゃがんでは切り、立っては束ね、またしゃがむ。
腰にくるけど、心は不思議と穏やか。
風の音と、鳥の声と、遠くの山の稜線。
「これぞ農業の原点だなぁ」と思える瞬間です。
刈り取ったえごまは乾燥が進んでいて、触ると“カサカサッ”といい音。
茎を揺らすと、黒い実がポロポロと落ちていきます。
これが、健康食品でおなじみの「えごまの実」。
手のひらにのせると、小さいのに存在感があるんですよ。
まるで“努力の結晶”みたいにキラッと光って見えます。
🚜 脱穀から選別までの地味だけど大事な工程
次は脱穀機の出番!
赤い機械に刈り取ったえごまを入れていくと、
「ガタゴトガタゴト…」というリズムとともに、
枝と実が勢いよく分かれていきます。
この音を聞くと、なぜかワクワクしてしまうんです。
農家にしかわからない“収穫の音フェチ”ですね(笑)

脱穀が終わったら、今度は手作業でふるいにかけます。
大きなゴミを取り除いて、
細かな塵を唐箕(とうみ)で風に飛ばす。
昔ながらのやり方ですが、これが意外と楽しい。
風の強さで粒の動きが変わるから、
「お、今日は北風で調子がいいな!」なんて
一人で実況中継を始めてしまいます。
こうして残った黒い粒たちは、
まるで小さな宇宙みたいに光を反射して、
「よくここまで頑張ったね」と言いたくなるほど。

☀️ 天日干しと太陽の力
ふるいと唐箕を終えたえごまは、最後に天日干し。
シートに広げて、太陽の光をたっぷり浴びせます。
この工程があるだけで、香りと保存性がぐんと上がるんです。
黒光りする粒たちを見ていると、
まるで五泉の秋そのものが詰まっているような気がしてきます。

「今年は少ないけど、ちゃんと繋がってる。」
そんな実感が湧いてくる瞬間です。
このえごまは、来年の“種”として大切に保管します。
またここから、次の季節の物語が始まるんです。
🔥 収穫後のご褒美タイム
さて、作業を終えたら、恒例の「リセットタイム」。
今日も焚き火を準備して、火をつけます。
「ボッ」と炎が上がる瞬間、
一日の疲れがスーッと消えていくような気がする。

夕暮れの田んぼを背景に、
パチパチと薪が弾ける音を聞きながらただ火を眺める。
何も考えず、ただ炎の揺らめきに心を預ける。
これが最高の癒しです。
そしてこの日の“メインイベント”は、秋刀魚!🐟
七輪でじっくり焼いて、外はパリッと中はふっくら。
少し塩をふって、一口。
うーん、秋の味覚がしみる…!
焚き火の炎と秋刀魚の煙、
そして夜空に浮かぶ星の下で食べる一口は、
どんな高級レストランにも負けません。
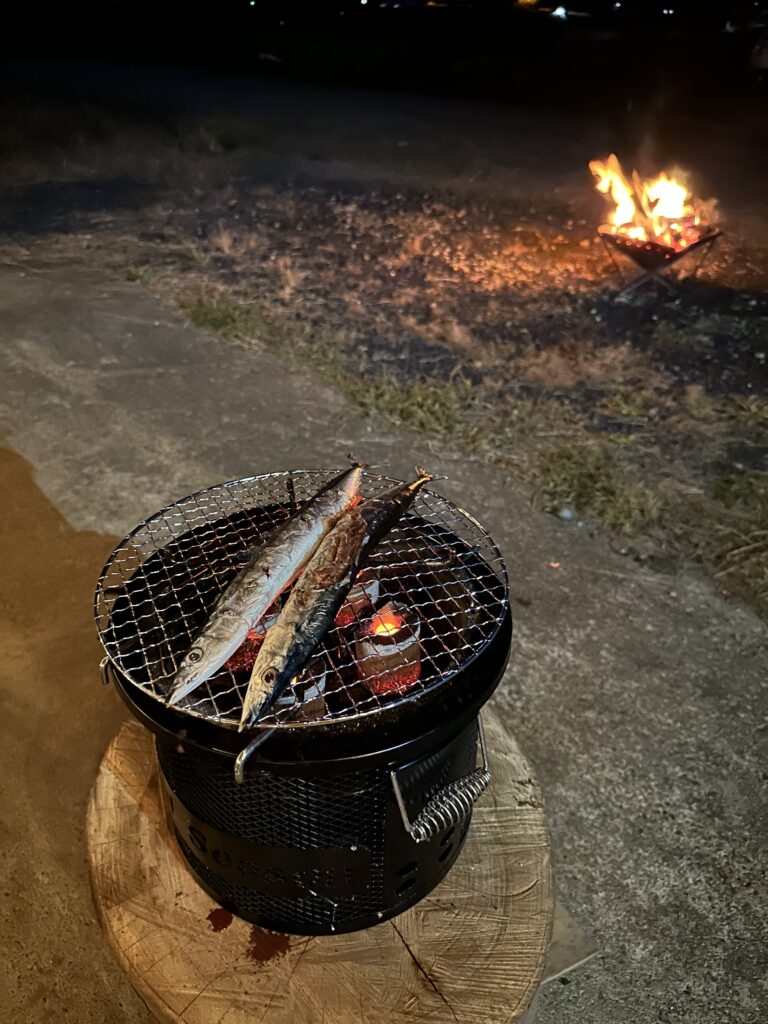
🌙 農業って、やっぱりいい。
夜、工房に灯る明かりを眺めながら、
「今日も生きてるなぁ」って感じる。
収穫が少なくても、手間がかかっても、
こうして自然と向き合っていられることが幸せなんです。

農業は“結果”より“過程”。
うまくいかない年も、全部が学び。
えごまが全滅しても、心まで枯れることはありません。
むしろ、「また来年が楽しみだな」と笑っていられる。
🌱自然に教えられ、
🌾風に励まされ、
🔥火に癒やされる。
そんな一日を過ごせることに、心から感謝。
さあ、明日も田んぼでがんばるぞ!
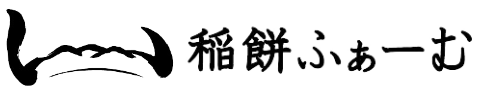





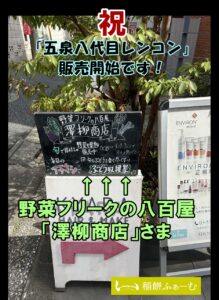



コメント